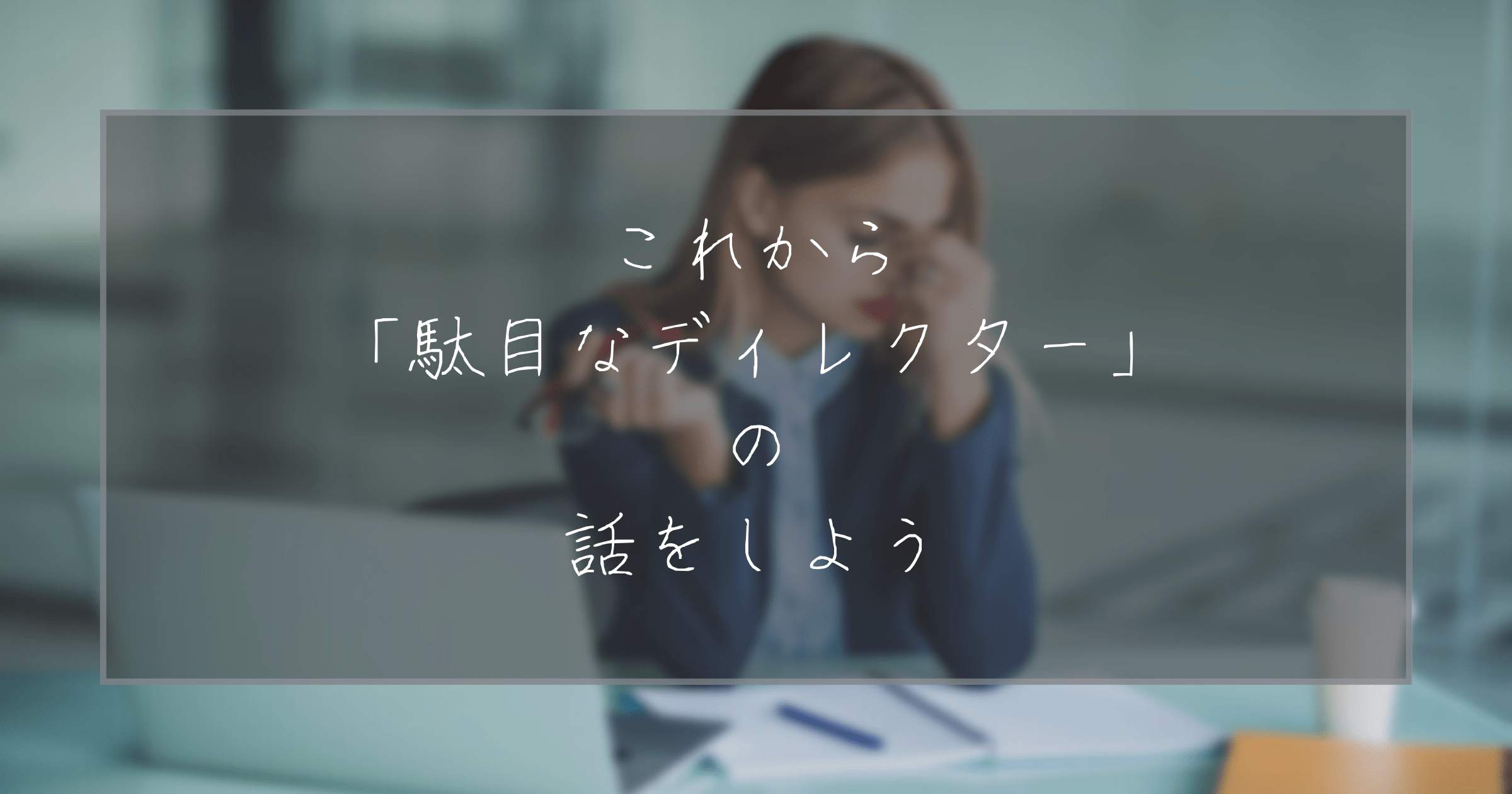世の中には不思議なことがあるもので、かつての同僚に、まるで迷子の子犬のように右往左往するディレクターがいました。
その人が、業界でも度々話題になるZグループのY社へと華麗なる転身を遂げたらしく「肩書だけで仕事ができなかった人を良く採用したなー」と、コメディ映画の一幕を見ているような気分でした。
多くの同僚達の探偵魂が疼きます。
当時の会社とY社は業務上のデータ連携を行っており、内部事情に精通した人材への需要があることは想像に難くありません。
当時の会社には、元Y社の産業スパイのような経歴を持つ人々が多々在籍していましたしね。
この出来事をきっかけに、昔書き綴った「残念なディレクター論」を思い出し、押入れの奥から引っ張り出してみました。
埃をかぶったその原稿を読み返しながら、改めて感じたことがあります。
ディレクションの本質論
ディレクションという仕事は、一見すると誰にでもできそうな職種です。特別な資格も必要なければ、専門的な技術スキルも必須ではない。
しかし、これこそ落とし穴なのです。この仕事の本質は、その人が持つ「人間力」というブラックボックスに完全に依存しがちだからです。
人間性が豊かで、周囲への配慮ができる人がディレクションを手がければ、魔法のようにプロジェクトが円滑に進行します。
一方、自己中心的だったり政治的で高慢な人間がその座に就くと、周囲は災害現場と化します。
まさに天国と地獄の分かれ道。
振り返ってみると、当時の職場環境は決して恵まれたものではありませんでした。
「この人ならディレクションを任せられる!」と胸を張って言えるレベルの人材が、残念ながら見当たらなかったのです。
これは組織としては致命的な状況でした。
その後、転職を経て新しい環境に身を置くようになってから、興味深い発見がありました。
仕事の進め方が不器用な人々との遭遇頻度が明らかに増えたのです。彼らを観察していると、どうやらディレクションという職種に根本的に適していないのではないかという疑念が湧いてきました。
この経験を通じて、ディレクションについて改めて考察をまとめる必要性を感じたのです。
優秀なディレクターの超人性
この職業の面白いところは、対人関係への依存度が異常に高いことです。
そのため、本当に優秀な人材は時として常識の枠組みを軽々と超越してしまいます。彼らの思考回路や行動パターンは、凡人には理解しがたいレベルに達していることがあります。
記事の最後に紹介する参考リンクには、そんな超人的なディレクターの実例が詳しく記載されています。ぜひご一読いただければと思います。
実際、私が過去に一緒に働いた何人かの優秀なディレクターたちも、似たような行動原理を持っていました。
彼らは常に戦術を駆使し、既成概念を打ち破る強さを備えていたのです。
そんな彼らの姿は、今でも私の記憶に鮮明に残っています。
さあ、それではダメなディレクターという名の迷子たちの生態について、詳しく探っていくことにしましょう。
残念なディレクターの生態観察
見ていて思わず目を覆いたくなる瞬間
職場で日々繰り広げられるディレクションという名の茶番劇。そこには思わず「おいおい、大丈夫か?」と心配になってしまうような光景が数多く存在します。
まず驚愕するのは、自分が生み出したものが世に放たれた時の姿を全く想像できていないという現象です。
まるで料理人が新作料理の味見をせずに客に料理を出すような、恐ろしい光景が日常茶飯事で展開されているのです。
興味深いのが、計画という概念が存在しない世界で生きている人々の存在です。
彼らは無計画を堂々と遂行しようとします。まるで地図を持たずに未知の土地へ冒険に出かけるような、ある意味で勇気ある行動と言えるかもしれません。
キャパシティの概念も彼らの辞書にはありません。
自分たちの能力を遥かに超えた仕様を平然と考案し、手に負えない状況になっていることに気づかない。これは現代版イカロスの翼とでも呼ぶべき現象でしょう。
組織運営においても、独創性は光ります。
小さな案件に企画担当者を3人も投入するという、まさに「船頭多くして船山に上る」を地で行く采配。1人あたりのマンパワーが0.33人になるという、数学的にも興味深い現象を生み出しています。
創造性の面でも、彼らは独特のアプローチを取ります。
オリジナルな企画を考える代わりに、他社サービスの完全模倣に走るのです。根本的なイデオロギーの違いを無視して移植しようとするため、当然のことながら水と油のような結果を招きます。
深層心理に潜む問題の核心
これらの表面的な現象の背後には、より深刻な問題が横たわっています。
クライアントの言いなりになるか、制作者の言いなりになるかという二択思考に陥り、自分自身の見識や企画力を放棄してしまう傾向があります。
まるで意志を持たない人形のような働き方です。
時間管理の概念も彼らにとっては謎に満ちた領域のようで、期限を明確にしないまま作業を進めます。
これは時間という概念から自由になった、ある意味で哲学的な生き方と言えます。
コミュニケーションにおいても独特のスタイルを貫きます。すべてを口頭で済まそうとする姿勢は、文字という文明の利器を拒絶した原始的な美学の表れかもしれません。
なぜ彼らは迷子になるのか?
組織の闇に潜む真の原因
働き方の改善が行われない背景には、実に人間らしい理由が隠されています。
まず、ロールモデルの不在という根本的な問題があります。業種未経験者にとって、これは砂漠で水を探すような困難な状況です。誰も正解を教えてくれない中で、手探りで進むしかないのです。
さらに厄介なのが、即席で仕事を奪って悦に浸るテイカーな人々の存在です。彼らは本来やるべき仕事をやらなくても良いという錯覚を周囲に与え、責任の所在を曖昧にしていきます。
他人の努力を知らずに自分勝手に行動し続ける人々も、組織の健全性を蝕む要因の一つです。彼らは自分が見えている世界だけが全てだと信じ込んでいるのです。
個人的に最も印象深いのは、当時度々に耳にした「何を知っているべきなんですかね〜(ヘラヘラ)」という言葉です。この一言には、学習意欲の欠如と責任回避の姿勢が見事に凝縮されていました。
興味深いことに、このような質問をしてきた人々の中で、素直にアドバイスを受け入れた人は確実に成長していました。
一方、他人に依存し続けた人々は自尊心だけが肥大化し、より深刻な状況へと陥っていったのです。
問題解決という試金石
真の能力は、問題が発生した時に顕著に現れます。
優秀な人材は「これを解決するには何が必要ですか?」と素直に質問できる謙虚さと臨機応変さを持っています。
自分の無知を認めることの難しさを理解しながらも、それを乗り越える勇気を持っているのです。
しかし、多くの人は自分が知らないという事実を開示することに躊躇し、結果として安直な対応を繰り返してしまいます。
そこからは学びも成長も生まれません。
光る人材の共通項
有能なディレクターが持つ8つの武器
一方で、継続的に成果を出し続ける人々も確実に存在します。
彼らが持つ特徴を観察してみると、興味深いパターンが浮かび上がります。必要なことを機敏に察知する気づき力は、空気を読むセンサーのような能力です。
彼らは状況の変化を敏感に感じ取り、適切なタイミングで行動を起こします。
少し先を見据えた行動計画を立てる先回り力も重要な要素です。チェスのように、相手の手を数手先まで読む戦略的思考と言えるでしょう。
関係各所との調整を巧みに行う中和力は、まさに外交官のようなスキルです。異なる利害関係を持つ人々の間に立ち、全体最適を実現していきます。
問題が発生した時に改善方向へ導く解決力は、彼らの真骨頂とも言える能力です。
責任を追及するのではなく、建設的な解決策を見出そうとする姿勢が、チーム全体の士気を高めます。
企画力という特殊スキル
企画分野に特化した能力として、収益構造への深い理解があります。
これは単なる創造力ではなく、ビジネスの本質を見抜く洞察力と言えるでしょう。
定数的事実に基づく企画立案も、彼らの特徴的な思考パターンです。
感情や直感に頼るのではなく、データという客観的根拠を重視します。
もちろん、これらの能力は業種によって求められる度合いが異なるため、一概に評価することは難しい部分もあります。
終わりに|接着剤としてのディレクター論
ディレクション自体は、決して高度な専門技術を要する仕事ではありません。
求められるのは、むしろ普通の人間が持つべき基本的な能力です。
筆者が考える理想のディレクターは、接着剤のように人と人を結びつける存在です。組織の潤滑油として機能し、全体を円滑に動かしていく役割を担います。
サービスの仕様について言えば、残念な人材が関わると複雑で煩雑なものになりがちです。
一方、優秀な人材が手がければ、驚くほどシャープで使いやすいものに仕上がります。
この違いは、同じ問題に直面した時のアプローチの差に現れます。
平凡な人は機能を足そうとしますが、優秀な人は機能を引こうとします。引き算の方が遥かに高い能力を要求されるため、能力差が顕著に現れる事象の現れです。
日本人の教育的背景として、「前進一方で完璧な結果を一気に出そう」とする傾向があります。
しかし、サービス運用の現実は「一進一退の連続」です。
真に必要なのは、前進と後退を繰り返しながら最善の結果を求めるという柔軟な思考と胆力です。
完璧主義を捨て、改善のサイクルを回し続ける粘り強さこそが、優秀なディレクターの条件とも言えます。
下記がそう言ったこと踏まえた職業適性の賢者と愚者の最たる比較だと思います。
先まわりと論理展開+責任を追う覚悟だけでも成果に結びつき、企業の収益を獲得しやすいのは事実です。
上のやり取りの通り、会社に合ってる云々は関係ありません。近年色々なところで見かけますが、問題を見つけるより、あげつらって問いただし、優越感に浸りたい他罰的な大人子供が非常に多いのが現実です。
目的論的に考えて、普通の事すら出来ないという状態から卒業しましょう。